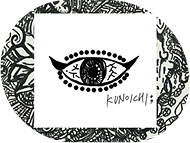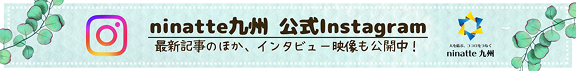「地域伝統を守りつつ、時代に合った人形づくりを」今宿人形師 佐藤圭比古さん

“地域伝統を守りつつ、時代に合った人形づくりを“
今宿人形『人清(にんせい)』4代目人形師 佐藤圭比古(さとうよしひこ)さん
~ルーツは信仰心。だけれど猿面を、インテリアとしても楽しんでもらえるように~

福岡県福岡市七隈の道路沿。
落ち着きのある店前に並べられた、色とりどりの猿面たち。
赤・青・黄色・緑と、かなりポップな印象である。
ここは、福岡市七隈で営まれる『今宿人形 人清(にんせい)』
今回お話を伺ったのは、『人清』4代目、人形師の佐藤圭比古(さとうよしひこ)さん。代々受け継がれる今宿人形の歴史を担う伝統継承者の1人である。
圭比古さんは福岡市城南区七隈出身であるが、2代目の大橋重雄さんの世代まで、この人形作りは、その発祥地である福岡市西区今宿にて営まれてきた。その大橋重雄さんにより、明治38年に開かれた節句人形工房『人清』の開業こそが、今宿人形のはじまりなのだそう。そして3代目、佐藤由美子さん(圭比古さんのお母様)の世代に、ここ七隈へ移転し現在の圭比古さんへと継承される。
取材にあたり、今宿人形の制作地を七隈に移したことに疑問を感じ、それには何か特別な理由があるのか尋ねてみると、実はすぐ裏手に人形づくりに適した粘土がとれる山があるのだそう。そこでは、白い土と赤い土がとれ、人形の種類やサイズなどに合わせて、粘土を使い分けながら作品を作っているという。
共に人形師である父母をもち、特に母の家系においては、人形の型の制作も担っていた。そのため圭比古さんは、幼少期から粘土造形をはじめ、今宿人形、そして博多人形にも触れながら育つ。人形制作における一連の流れを見ながら成長した圭比古さんにとって、身の回りに人形があることはごく普通の光景であった。
今宿人形の歴史は意外にも博多人形より古く、今宿人形が博多人形の母体になった民俗土人形であるとも言われている。驚いたのが、今宿人形や博多人形として制作された型であっても、その同じ型を他の地域に貸し出すことがあるのだという。
形の原点は九州にあっても、その地域特有の異なる表情が人形に与えられるそう。同じ型をとっても、全く同じ形にはならない。
「そのようなことも人形の魅力、おもしろさのうちの1つではないでしょうか」。
と圭比古さんは語ってくれた。
“猿面のルーツは、人々の信仰心“
福岡市早良区に、猿田彦神社(さるたひこじんじゃ)という神社がある。そこでは、60日ごとの庚甲(かのえさる)の日に行われる庚甲祭(こうしんさい)にお参りに行くと、この猿面を授けてもらうことができるのだそう。この庚甲祭における奉納を、初めに行ったのが、”今宿人形 人清”だ。そして、今宿人形のルーツを辿ると、そこには人々の“信仰心“と深い結びつきがある、と圭比古さんは語る。
今宿人形と信仰にはどのような関係が築かれてきたのだろうか。
圭比古さんに、この今宿人形と信仰心の繋がりについても伺ってみた。
「そうなんです。猿面のはじまりは人々の“信仰心“からなのです。宗教とは、また少し違うのですが、いわゆる”魔除け”のような役割を担っています。“災が去る(サル)“という意味を兼ねてですね。昔はもっとこの猿の目が、魔を寄せ付けないように"鋭く睨みをきかせたような目”をしていたんですよ。今は、徐々に柔らかくなってきているのですが」。
このように、今宿人形のルーツは、元々、人々の信仰心にあるのだそう。魔除けとして継承されてきた今宿人形と信仰心のつながりは、たくさんの人々の支えとなってきたのだろう。
“人形にまつわる伝統文化が薄れていく”
3月の“ひな祭り“や、5月の“こどもの日“など、伝統的な「人形」にまつわる行事が、日本には存在する。しかしながら、時代の流れとともに、かつて伝承されてきた生活文化が、徐々に薄くなっているのではないか、と圭比古さんは捉える。
「ひな人形やキンタロー人形など、日本文化として身近にあったものが、もう今はなくなってきているようにも感じますね。そういったことに対して少し淋しさを感じます」。
圭比古さんの一言には、深く考えさせられるものがある。
たしかに、わたしたちの生活や年中行事と共にあった人形文化は、時代の流れや生活洋式の違いによってその存在が遠くなってきているように感じる。人形文化に限らず、現代社会における人々とさまざまな伝承文化の間に、距離が生じつつあるのかもしれない。“かつて日本人の日常と共にあった文化“への意識が薄れ、少しずつ「過去のもの」になりつつあるのではないだろうか。圭比古さんは、時代や人々の意識の変化に危機感を覚えながらも、次の世代にもこの今宿人形を残していくために、さまざまな工夫と努力を重ねている。


“圭比古さんが考える、これからの今宿人形”
圭比古さんに、これからの今宿人形と人々に対する想いについて語ってもらった。
「まず、今ここにある今宿人形猿面を拡大させるためには、現代の家に馴染むような猿面も創っていく必要があると思うのです。今はもうどこの家も昔の古民家とは違いますよね。そのようなことも含め、猿面を"インテリア”として手に取ってみて欲しいのです。信仰や歴史に関しては、今宿人形に深く関心を抱いてくれたときに、後付けで知っていただけたら良いわけで。どことなく根付いてしまった古くさいイメージは払拭していきたいのです」。
このように、時代の移り変わりに沿った今宿人形を創作していきたい、と意欲を語ってくれた。
「もっと人形を、身近な存在にしたいです。そのために、若い方々やアーティストさんなどともコラボレーションをして、カラフルなデザインの猿面であったりポップなものを創ってみたり。大切なことは時代の流れを感じ取ることですね。オリジナルで、これから色々試していけたらいいなと思っています」。
伝統工芸品としての今宿人形を大切にしながらも、それらの型にとらわれすぎない柔軟な心持ちと、ときには時代に合わせながら、その存在を守り続けることへの強い意志を圭比古さんに感じる。
映画『猿の惑星/キングダム』とのコラボレーション”
2024年5月、映画『猿の惑星/キングダム』と今宿人形猿面のコラボレーションが実現した。『猿の惑星』に合わせて制作された猿面たちは、福岡県限定の特別な立体看板に飾られ、映画の試写会や公開記念イベントで大注目を浴びた。制作された立体看板は、ユナイテッド・シネマ・キャナルシティ13で展示され、「このために100体くらいの猿面を制作したんですよ。大変でした」と、圭比古さんは笑う。
この『猿の惑星』とのコラボレーションも、圭比古さんにとっての新たな挑戦であった。今宿人形とともに歩み、迷わず挑み続ける姿勢は、伝統工芸品における継承者として、また、ひとりの創作家として、筆者の目に輝いて映り、その奥に圭比古さんの文化存続への強い思いと、使命の大きさを感じた。

“圭比古さんの考える、これからの今宿人形のすがた“
古くからの伝統を守りつつ、アーティストとのコラボレーションや時代に合わせた新たな試みを重ねる圭比古さん。古くからの概念に固執せず、さまざまなニーズに応えるその柔軟な姿勢に、人形づくりの新たな可能性を感じる。幅広い世代の方に今宿人形を身近に感じてもらうこと、そして気軽に手に取っていただけること。伝統継承者圭比古さんの、人形づくりに込める強い想いが伝わってくる。
最後に、圭比古さんはこう語る。
「人形の本来のすがたは家に飾ることで、その持ち主の心が安らぐこと。そこなんですよ」。
優しいお人柄で、4代目今宿人形師として、ひたむきに人形制作に向き合い続けている佐藤圭比古さんの今後の作品が、とても楽しみである。
次はどのような猿面が誕生するのだろうか。
今後、福岡県那珂川市にて、古民家ギャラリーも開く予定もあるのだとか。見学料は無料、一般の方々に向けて公開されるのだそう。
佐藤圭比古さんの次代に向けた人形制作、また新たな試みと取り組みに注目し、九州の伝統工芸品今宿人形に、是非一度触れていただきたい ——。