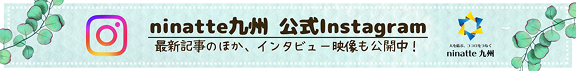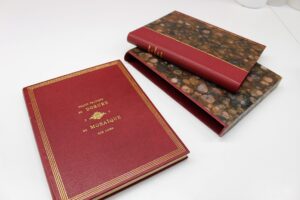すべての人へ同じ品質を届ける職人の技 吹きガラス工房『粋工房』

100年のガラスの歴史を継ぐ『粋工房』
緑豊かな道を進むと赤い看板に「粋工房」の文字が見えてくる。宗像市田野の地で、福岡の工芸品である『福岡積層工芸硝子』の製品を作っている工房だ。
色の違うガラスを重ねて表現する福岡積層工芸硝子はおよそ100年の歴史をもち、福岡県知事指定特産民工芸品に指定されている。
「福岡はガラスの置物が多い地域なんですよ。元々はガラスの生活雑器を作っていた職人さんが遊ぶ感覚でガラスの置物を作って、意外にもそれがヒットしたっていうのがきっかけなんです」
そう話してくださったのは、粋工房で制作アシスタント兼マネジメントをされている伊藤伸晃さんだ。
長い歴史をもつガラスの技術を継承しながら、現代の生活にもなじむ新しい製品を作り続ける粋工房に、ガラス職人という仕事や製品作りについてお話を伺った。

地元の風土を色に落とし込む『宗像びーどろ』

粋工房の店内には、端午の節句の兜、桃の節句の雛人形、お正月の鏡餅に各干支の人形など、ガラスの置物としては目新しい商品が多い印象をうけた。
その店内のなかでも目を引くのが『沖ノ島朱(あか)』という鮮やかな朱色のグラスだ。この『沖ノ島朱』というカラーは、粋工房さんがオリジナルで制作された『宗像びーどろ』のうちの1色で、他にも『大島翡翠』、『金の岬天色(あお)』と全3色がある。
『宗像びーどろ』を作ろうと思ったきっかけは、「神宿る島」宗像・沖ノ島とその関連遺産群が世界遺産に登録されることだったそうだ。宗像にまつわる特産品を作れないか考えていたときに、お知り合いの方が作っていた”沖ノ島の塩”を原料に入れてみたところ、いつもの赤とは違うオリジナルの赤ができたのだという。
「今まで工房で作っていた赤と比べると、より明るく朱色に近い色になったんです。なぜ普段の赤色と違うのか、沖ノ島の塩の成分を調べてもはっきりは分からないみたいです」と話してくれた。元々、宗像の市章である赤、青、緑の3色をそれぞれ作りたいとも思っていたため、残りの青、緑も開発を進めた。
数年間の試行錯誤を繰り返し、大島の海岸の砂から作られた緑『大島翡翠』が完成。そのまた数年後、養殖中にだめになってしまった鮑の殻から作られた青『金の岬天色』が完成。ようやく3色すべてが揃ったのだという。
地元の素材から生み出されたガラスは、宗像らしさがつまった製品として多くの人に喜ばれるものになっている。
粋工房の”職人”とは

宗像びーどろのグラスは飲み口が滑らかで柔らかく、見た目からの想像よりかなり軽い。グラス全体の厚みを薄く均等に仕上げる職人の技術だ。今粋工房には3人の職人がいるが、技術の継承のためにも新たな職人を募集している。
粋工房の職人には”ある程度のスピードで同じ品質のものを作り続けられること”が求められる。
店頭はもちろん、ネットからの注文も受けている粋工房では、同じ製品を繰り返し、安定した品質でお客さんまで届けることが大切になってくるからだ。
「炉の中のガラスを竿に巻きつけて取る作業も、まず必要な量だけを取るということが難しいと思います。グラスを作る時もガラスの量が変わるとサイズが変わってしまいますし、職人が2人がかりで作る置物もあるので、最初はそういう基本的な部分を習得することからですね」
実際、一定のガラスの量を取り制作するまでに2~3年はかかるものだそうだ。
1250度に熱せられた炉の前に立ち、金属の竿にガラスを巻きつけて作業するのは結構な力仕事で、夏場はかなりの暑さになる。
どれも決して楽な作業ではないが、粋工房には70代のベテラン職人や女性の職人など、頼もしい先輩がいる環境なので、性別や年齢にとらわれることなく、未経験者でも一歩を踏み出せる工房なのではないだろうか。
ガラス製品や職人という仕事に興味のある方は、ぜひ一度工房を訪ねてみてほしい。
伝統を残しながら、現代の生活に溶け込むものづくりを

夏祭りや体験イベントなど、地域の人たちが気軽に訪れられるような行事も行っている粋工房。
グラスやとんぼ玉、風鈴、箸置きなど、制作体験の種類も豊富で、幅広い年代のお客さんが体験にいらっしゃるそうだ。
「山の中にある工房なので、うち一か所だけじゃなく地域全体で盛り上がって人を呼び寄せていきたい」と伊藤さんは話してくれた。
また、歴史ある福岡積層工芸硝子の技術を残していくためにも、商品を手に取ってくれたお客さんを一番に思ったものづくりを続けている。
「長く技術を残していくためにも、新しい製品作りは積極的に行っています。うちは置物も生活雑器も、同じ品質のものを1500個くらい作っていく工房なので。新しい製品を考えるときは、どうすればそこをクリアできるか柔軟に考えています」
粋工房へ取材に行く前までは、ガラス職人と聞くと斬新な発想で作品を作る人というイメージがあった。
しかし、誰がどの商品を手にとっても同じように満足できる製品を作るということにも、職人の繊細で確かな技術が詰まっている。
商品を使う生活者のことを一番に考えながら、柔軟に伝統のものづくりを続ける粋工房だからこそ、今もこれからも幅広い層のお客さんに選ばれていくのだろう。