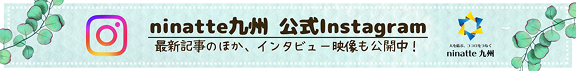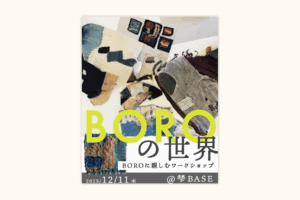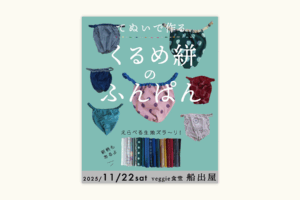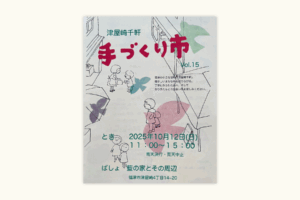糸を紡ぐように 「好き」がたぐりよせた私の生き方~縫いもの作家nuぬう~

『ふるくてあたらしいくらし』をモットーに、布にまつわる活動しているnu(ぬう)さん。(以下、ぬう)
ぬうさんが出店するマルシェでは、くるめ絣のターバンやふんぱん(ふんどしパンツ)、自身で染めた草木染めのストール、はぎれと糸くずのブローチなど、個性豊かな手作りの布小物たちが並ぶ。
まっすぐな眼差しとキラキラした表情で話すぬうさんからは、素材や手しごとへの愛が溢れ、小物たちからもどこか生命力のようなものを感じる。
ぬうの小物を身に着けた友人が登場すれば、「似合う〜!!」と大歓声。はじめましてのお客さんも一緒に、「素敵ね!なにで作ったの?」と会話が弾む。
ぬうのマルシェテントには、いつも和やかな空気が流れている。
そんな『ぬうらしい』世界観は、どのようにして創られたのだろうか。
ぬうとしての歩み、そしてこれからの未来について話を伺った。
ぬうの現在地 ~『好き』から広がる輪~

”流木や竹を組み手作りした卓上の簡易機で葛布(くずふ)を織る。ワークショップに参加した方たちの作品。
ぬうのおもな活動は、マルシェへの出店、ワークショップの主催、衣服のオーダーメイドなど。
布にまつわるさまざまな活動を通して感じるぬうの役割は、『きっかけ作り』なのだそう。
「ワークショップは、身近にある材料とちょっとした工夫で、『自分でも作れるんだ!』ということを知るきっかけになったらいいなと思っています。自分で作る楽しさを体感したら、そのものに愛着がわいてきますよね。それを使っていけば、なおさらです」
ワークショップの内容は、くるめ絣を使った『ふんぱん』や『スヌード』づくり、着古した服から作る『布ぞうり』、原始機(げんしばた)で織る『裂き織りベルト』などなど・・・ぬうらしさが光るものばかり。
「ワークショップでは、教えるというより、手作りの面白さを一緒に味わっています。人が集まって一緒に何かを作るって、本当に豊かな時間です」
その言葉のとおり、誰よりも楽しそうに手を動かすぬうさん。黙々と集中したり、時折大笑いがおこったり・・・終始和やかな雰囲気であっという間に時が過ぎていく。
自分の手で作り上げた作品を愛でるみなさんの表情は、なんとも幸せそうだ。
「布ぞうりは、持参してもらった着古した服で作ります。一度は捨てそうになった服を、自分の手でよみがえらせる。アップサイクルの楽しさを体感して、ほんの少しでも、ものを無駄にせず上手に『使い切る』ことへの意識に繋がったらいいですね」
ぬうさんがワークショップで扱う布は、おもに綿などの自然素材や、くるめ絣など昔から作られ続けているもの。『純粋に好き』で使っているという布たちには、こんな思いも込められている。
「綿は植物なので、食べ物と同じように自然界の恵みからできています。種から育てて収穫して糸にして・・・。布になるまでにものすごい時間と人の手がかかっていることが想像できます。
では、普段何気なく身につけているその服は、どうやってできている?原料は?値段と見合っている?・・・など、衣食住の『衣』について考えるきっかけになったら」
なんでも簡単に買えて消費されていく時代だからこそ、一度立ち止まって考える『衣』のこと。ワークショップでの『きっかけ』と『体感』を経て、衣を手に取るときに見える景色が少し変わってくるかもしれない。
「くるめ絣は、地産地消というか、やっぱり住んでいるその土地のものを大事にしたいという思いがありますね。地元にこんな素敵な織物があるんだって、知るきっかけになったら嬉しい」
くるめ絣の工房へは幾度となく足を運び、職人さんたちとの関わりを大切にしている。
「同じ工房でも、訪れるたびに新しい発見がある。そのときの状況というか、世の中の流れも、どんどん移り変わっているし。職人さんの思いを知ること、自分の目で見て感じることで、作るものに心が宿る感じがあります」
その布の良さや特徴だけでなく、歴史や作り手の思いまでのせて伝える。ぬうさんが紡ぎ出す言葉に惹かれる理由のひとつだ。

”久留米絣の織元で布を選ぶぬうさん。まるで宝探しのよう。
一方、制作活動においては、自身で『染め』もしている。
「季節ごとに身近な山や畑で採れる植物の葉や枝を使って、『草木染め』をしています。藍をはじめ、栗・柿・枇杷の葉・ドクダミ・ヨモギなど・・・いろいろ試しましたね。
じっくり時間も手間もかかるけれど、植物たちがくれる思いがけない色の不思議を目の当たりにすると、『また次はこれで染めてみよう!』と試さずにはいられない。それが草木染めの愉しさですね」
たとえ同じ植物を使おうと、同じ色にはもう二度と出会えない。植物がもたらしてくれる色は、実に神秘的で美しい。

”草木染めのスヌード。オーガニックコットンのガーゼ生地がなんとも心地よい。
さらに、身近にある植物から糸を紡ぐ活動もしている。
その一つが「葛」。自然布のひとつである葛布(くずふ)は、自生している葛のつるから繊維を取り出し、糸にして布に織り上げたもの。
葛の季節は初夏~盛夏。
汗だくになりながら葛を採取し、数日間発酵させたあとに川の浅瀬で洗う。早朝の清流は真夏でもひんやり冷たい。真水と陽の光、それに人の手が加わることで、葛は光り輝く・・・。
その季節にしかできない自然の中の営みを、ぬうさんは仲間たちとともに味わっている。

”葛の川洗い。川面にゆらぎきらめく葛の美しさは、なんとも言葉にしがたい。
そうしてできた葛の繊維を、糸にしていく。
その糸でコースターサイズの織物を織ったり、アクセサリーを作ったり。葛を使ったワークショップでは、植物が衣の原料になること、身につけたり使ったりできる形になることが体感できる。
「ひと昔前の人たちは、季節ごとの手しごとをしながら、自然に沿った暮らしをしていた。身の回りにあるものを生かして、衣を自給していた。
そういう体験や発見ができる機会や、ともに楽しめる仲間の輪を、少しずつ広げていけたら。どんな形にしていこうか、私自身もまだまだ模索中なんですけどね」

”葛タッセルとシーグラスの耳飾り。自然のエネルギーがぎゅっとつまった、お守りのような存在。
好奇心と、探求心。子どものように純粋な『好き』の気持ちが、ぬうらしさを創っている。
それに引き寄せられて、人が集まる。愉しい時間を共有して、いい氣が流れる。
『豊かさ』がじんわり湧いてくるような、やさしい時間がここにはある。
しっくりくる暮らし、生き方を求めて

”布ぞうりはみんなで輪になり床に座って作る。
ぬうを本業にしたのは2020年頃から。それまでは、会社勤めをする傍らで、コツコツと準備を進めてきたのだそう。
「小さい頃からお裁縫が好きでした。でも、得意ではなかった。まっすぐ縫うとか、きれいに仕上げるとかが苦手で・・・全然上手にできなかったんですよ。『こんな服があったらなぁ』とか、イメージしたものを創造するのが好きでした。『よしっ作ってみよう!』って、わくわくするんです」
『好き』が原動力でずっと続けてきた布しごと。楽しさと同時に葛藤もあった。
「いつか本業にしたいという思いはあったものの、ふわっとしていて。会社勤めをしていた当時は、今のように『自分の好きを仕事にしていく』みたいな風潮があまりなかったし、そういう話をできる人が周りにいなくて、ひとりで悶々とすることも多かったですね」
そんな中、大きな転機がおとずれた。
2011年3月。東日本大震災、そして原発事故。
「衝撃的でした。はっきりと、意識が変わりましたね。仕事どうこうというより、暮らし方、生き方そのものへの意識が。
ただ単にものを作って売るだけではなく、そこに『付加価値』をつける・・・。伝えたい思いをこめて意味や温度を持たせる感じかな。ぬうの活動は、同じ方向を向いている人たちと繋がるための手段のひとつでもある、と考え始めたんです」
それからは、マルシェやイベントなどへ出店したり、布ぞうりのワークショップを始めたりと、着々と活動の輪を広げていった。
「既存の社会に依存せず、自分の頭で考えて、自分の足で立って生きる道を探し出した・・・。そんな感じです。そうしているうちに、そうやって生きている人たちと繋がりだしたんです」
人と繋がり、場所と繋がり・・・。ぬうさんが思い描く暮らし方・生き方が、少しずつ形になっていった。
そして、より自給的な暮らしを求めて移住。会社勤めも終え、ぬうとしてまた新たなステージに立ったのでした。
流れにうまくのり、穏やかにスムーズに事が進んできたように見えるぬうさんだが、頭の中では常にぐるぐると思考を巡らせ、迷いや葛藤と向き合っている。
「やっていることがあれこれあるので、『表面をただなぞっているだけになっていないか?深化しているか?逸れていないか?』などを常に念頭に置いています。わかりやすくひとつずつ特化して、それをもう一歩踏み込んだ所まで伝えていく。そんなアプローチの方法を思案して、実践して・・・気づきや学びは尽きません」
「ものに付加価値をつけることに関して、まだまだ自分の力不足な部分を感じています。そのものに込められたこだわりを、十分に伝えきれていない。いいものをいいものとして、それなりの価値があるものだと理解してもらい、喜んでもらう。そのためにはどんなふうに伝えたらいいか、日々模索しています」
生き方をシフトさせるために始めたぬうの活動は、思い描く世界をはっきりと見据え、着実に歩みを進めている。
その過程や寄り道もまるごと味わって、自分の生き方を愉しむ。ぬうさんを見ていると、そんな言葉がしっくりくる。
土とともに生きる

ぬうの現在の活動拠点は福津市。作業場を兼ねた自宅からほど近い場所に、畑を借りている。
「いつでも土に触れられて、自分の食べるものは極力自分でまかなう。そういう自給的な暮らしがしたかったので、移住先で畑をするのは絶対条件でした」
『ぬうのやさい畑』は、静かでゆったりと時が流れ、空が広く気持ちのいい場所にある。
無農薬・無肥料の自然栽培の畑には、かぼちゃ・なす・きゅうり・ゴーヤ・・・それに大豆やごまなど、さまざまな作物が実っている。
連日の酷暑と干ばつの中でも、力強く生きている作物たち。その姿を愛でるように、手に取り、声をかけるぬうさん。
「すごいですよね。こんなに土がカラカラなのに、花が咲き実がつく。たくましくて、かわいい。このごまの花。すっごく可憐でかわいいでしょ!」
ぬうさんにとって、畑は暮らしの一部であり、心がリセットされる場所。
作物たちの姿にパワーをもらい、『自分も自然の一部』だと肌で感じられることが、ぬうをつくる大切なエッセンスだ。

植物から糸を紡ぐ試みのひとつとして、綿花も栽培している。
「栽培している綿花から糸を紡いで、いずれは衣服の素材にしたい。今はまだまだ実験段階ですが、どんな形にしようかあれこれイメージをふくらませています」
ぬうさん自身の手で、種から育てた綿花。紡ぎ出された糸からは、温かみの中にもしっかりとした力強さを感じる。

”左から、葛の繊維・緑綿・茶綿・和綿。染色していない、綿そのものの色。
畑を始めてから、地域との関わりもより意識するようになったそう。
「地域の方との触れ合い方というか、地域に馴染む大切さみたいなものが、やっと少しずつ、身に染みて分かってきたような気がします。まずは、住んでいる場所のこと、人のことを知っていく・・・。その中で、自分ができることってなんだろうと考えています。田舎暮らしはまだまだ勉強中ですね」
『ふるくてあたらしいくらし』が紡ぐもの

”淡く美しい、和棉の花。
ぬうさんが思い描く未来は、どんなものなのだろう。
「私自身の暮らしでいえば、より自給的で土に近い暮らしをしたいですね。それぞれが自分の好きや得意を持ち寄って、それぞれの役割で無理なく生きる。その中で、衣食住を自給していけたらいいなって。そういう、『ひとつの村』みたいなコミュニティを築いていきたい」
『自分の役割』で生きるとは。ぬうさん自身も、悩みながら迷いながら、その手ごたえを探している途中だ。
出会った人たちと共有する時間は、遊びという名の『衣への挑戦』だと話すぬうさん。
「葛しごとや畑をしていると、場と人の力が合わされば、身の回りの循環で衣食住をまかなえるのだと実感しています。ひとりでは絶対に不可能。道のりは一歩ずつですけど、着実に、進んでいけます」
『衣食住の自給』と『循環する暮らし』。
果てしないようにも思える道のりを、ぬうさんはまっすぐ前を見て歩んでいる。
私たちにとっても、決して他人事ではない。今の暮らしがこの先もずっと続いていく・・・そんな保証はどこにもないのだ。
仕事としての、ぬうの展望はどうだろうか。
「ワークショップなど『伝え手』としての活動においては、じっくり衣服を制作したり、布になるまでの過程を体験したり・・・段階的に学びを深められる方法を模索しています。現在は一回で完結する単発のワークショップが主ですが、連続した講座も充実させていきたいですね」
「ワークショップの形も変わっていくかもしれませんね。教える・教わるみたいな縦の形ではなく、伝え合うような、横繋がりで輪になる感じだったり・・・新しい切り口のなにかが見つかるかもしれない。私が、というより、世の中がそんな方向に動いていくんじゃないかって思っています」
制作活動についても、ぬうさんはこう続ける。
「今は作りやすくて手に取ってもらいやすい小物や雑貨がメインですが、衣服のウェイトを増やしていきたい。服作りの側面ってあまり知られていないので・・・。オリジナルの衣を充実させることで、地元の織物や古くからある布や手しごとに親しんでもらう機会を増やせたらいいなと思っています。
染織の探求と温故知新の学びに終わりはありません」
『ぬう』は、仕事であり、暮らしであり、生き方そのもの。
自然と人、人と人、今と昔・・・。
糸を紡ぐように、いろいろな繋がりをうみだす。
ぬうは、そんな存在のように感じる。
ぬうさんが紡ぎ出す『ふるくてあたらしいくらし』のエッセンスは、私たちにとっても、生きていくための道しるべになる。そんなふうに思った。
nu ぬう
Instagram:https://www.instagram.com/nu_etsuko?igsh=enFxNDV3MjkzajU5
Facebook:https://www.facebook.com/robadayori
ワークショップや出店情報が随時アップされています。ぬうさんが綴る言葉が素敵なので、ぜひ覗いてみてください。
この記事の執筆者
福島県会津若松市出身。「モノ ・ コト ・ ヒト」を伝えて繋げるライター。
古布・久留米絣・自然布・リユース布・天然素材・天然染料を使った衣類や布製品を制作。
Facebook:https://www.facebook.com/robadayori
【開催終了】『BOROの世界』〜BOROに親しむワークショップ〜
nu(ぬう)さんによるBOROに親しみ、BOROを作る会の開催です。BOROのぬくもりと奥深さをぜひ味わってみてください!
2025年12月11日(木)11:00〜15:30
梺ベース
【開催終了】『縫う夜会』
nu(ぬう)さんによる夜の縫いもの教室です!金曜の夜にしっぽりと、素敵な時間をぜひ。
2025年12月5日(金)17:00〜20:00
veggie食堂 船出屋
【開催終了】てぬいで作る くるめ絣のふんぱん
福岡県の伝統織物「久留米絣」を使ったワークショップ
11月22日(土)10:30〜15:30
veggie食堂 船出屋
【開催終了】くるめ絣のあずま袋つくり
福岡県の伝統織物「久留米絣」を使ったワークショップ
10月17日(金)10:30〜15:30
梺ベース
【開催終了】津屋崎千軒 手づくり市
津屋崎で年に1度だけ開催されるイベントです!
10月12日(土)11:00〜15:00
藍の家とその周辺