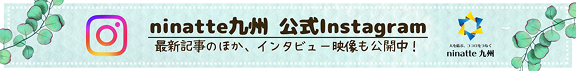息を吹き返した織物『箱崎縞』 香蘭女子短期大学准教授・尾畑圭祐

綿100%・縞や格子柄のシンプルなテキスタイル『箱崎縞(はこざきしま)』。この箱崎縞、実は終戦間際に一度途絶えている。今回そんな箱崎縞を約70年ぶりに復活させた尾畑圭祐(おばた・けいすけ)さんにお話を伺った。
福岡市東区箱崎。ここは元々漁師町で、漁業と農業が入り混じった地区だった。この地の主な交易品も海産品や農作物であったが、年貢物にも適し、箱崎の活性化につながる新たな産業を生み出そうという発想から『箱崎縞』が誕生したという。
しかし、戦時中の金属回収令で機織り機が潰され、箱崎縞も消滅してしまう。そんな幻と化した箱崎縞を、2021年に復活させたのが尾畑さんだ。
原点。そして模索した進むべき道

現在、香蘭女子短期大学・ファッション総合学科で准教授をしている尾畑さん。やはり幼い頃からファッションへの関心は強かったよう。
「中学生の頃には、当時の古着ブームもあり、よく大名(だいみょう)あたりに古着を買いに行っていましたね。それと私の祖母が和裁をしていたこともあって、幼い頃から服づくりにも興味があったように思います」
高校を卒業した尾畑さんはファッションを学ぶためにアメリカ・シアトルの学校へ進学。しかし、当時そこで学んだことはどちらかというと商業ファッション。
「シアトルには、NYのような先端ファッションを生み出すためのカリキュラムはなく、どこか違和感を感じながらも、ウインタースポーツが盛んなその地で当時はスノーボードにハマってましたね。卒業後の進路についても、ウインタースポーツウェアの会社に入ろうかなと漠然と考えたりして。でもやっぱり、そういった商業的なファッションを追うのではなく、しっかりと自分らしい服づくりがしたいなと思って。そこで知人に相談したところ『それなら東京の文化服飾学院で学びなおしてみては』とアドバイスをもらい、日本に戻ることを決意しました」
帰国後、“自分の表現としての服づくり”に取り組み始めた尾畑さん。表現としての服に向き合った際も、やはり昔から好きな『古着』が着想の基盤となっていたという。
「0からデザインするのではなく、古着のように昔のものを受け継ぎながら現代に合わせて再デザインするということが楽しかったですね。日本のアパレル企業でデザイナーとして働いていた時も、無数の古着の資料を手に取ってのめり込むように勉強しました。古着の生地感と現代の生地感は全く違うので、昔の風合いを活かした生地をつくりたいと思いオリジナル生地の制作もしていましたよ。ですので現在『箱崎縞』でやっていることも、私にとってはその頃と大きくは変わらない。形やデザインだけではなく、布だけで十分説得力のあるものがつくれると思うんです。手間がかかることはどんどん合理化される時代だからこそ、手間をかけてつくられた生地や古着により一層魅力を感じます」
『箱崎縞』との出会い

一度は消滅し、その存在すらも忘れ去られようとしていた『箱崎縞』。そんな幻のような箱崎縞と尾畑さんはどのように出会ったのだろうか。
「博多織の修行のため学校に通っていた時に、ふと『博多織ほど高級なものではなく、普段着にもいかせて、かつ私がまだ知らない綿素材の織物はないものかな』と考え、情報収集を始めたんです。その頃はお金はないけど時間はいっぱいあるような状況だったので(笑)、図書館で専門書を開いて地道にその素材を探していましたね。そんな中、過去の糟屋郡の経済紙に書かれた『箱崎縞が名産』という文字が目に留まり、この『箱崎縞』を詳しく知りたいと資料探しを始めました。ところが、市や県に問い合わせても、誰も何も知らない。それでも諦めず、独自に情報を集めていたところ、博物館でそれらしい長法被(ながはっぴ)を見つけたんです」
遂に実物に辿り着いた尾畑さん。ちょうどその頃から大学で働き始めたため、様々な学術的資料を取り寄せることが可能に。それらの資料に目を通す中で、箱崎縞復元の決め手となる文献を見つけた。それが、福岡女学院短期大学が出した紀要の中の徳山怜子・『庶民の布「箱崎縞」考』。この紀要に、箱崎縞に使われている糸の種類や番手のこと、当時ご存命だった織元へのインタビュー、更に箱崎縞の耳には印がついているということも記載されていたという。
「この紀要が箱崎縞を復元する時の証明になりました。これを読んだ後、再度博物館で見た長法被を見に行くと、ちゃんと箱崎縞の印が耳についていて、『ああ、やっぱりこれは本物だ』と確証を得ましたね。そして、紀要の中に『糟屋郡の資料館に箱崎縞が寄贈されている』との一文も見つけて、早速問い合わせて見に行きました。そこで箱崎縞復元の目的のために本物の端切れが必要なことを伝え、その提供をお願いしたところ、研究兼復元資料という形でその許可をいただけたのです。提供いただいた端切れをほどき、番手や種類を見たり紀要と照らし合わせたりしながら慎重に分析を重ねて、やっとの想いで箱崎縞が復活しました」
ずっとファッションの世界で服や生地についての知識を深め、真摯に服づくりに向き合ってきた尾畑さんだからこそ『箱崎縞』とつながり、現代に蘇らせることができたのだろう。
生活に寄り添ったテキスタイル

長年の苦労の末に復活した『箱崎縞』。このテキスタイルの特徴は、ずばり“特徴がないこと”だと尾畑さんは語る。
「伝統的な古い織物にはそれなりの特徴があるんです。そしてそれらの大部分は高級品扱いなのですが、箱崎縞はこれといった特徴がなく、そもそもが“使うための布”だったんですよね。だから難しい技法などは使わず、縞と格子だけで表現していて、厳しい規格もないから、それぞれに微妙に表情が違う。そういった立ち位置の布なので、逆に現代の画一化されたプロダクトが多い中では良い意味で差別化が図れています」
優しさと丁寧さに包まれる空間『メゾンはこしま』

『メゾンはこしま』を代表するお菓子SHIMA。珈琲は自家焙煎。
“使うための布”という箱崎縞そもそもの性質を大事にしている尾畑さん。長い時を経て復活した箱崎縞は一見貴重なもののように思われるが、尾畑さんとしては多くの人が気軽に手に取り、日常で使ってほしいという。
そんな箱崎縞の商品を実際に手に取れるのが、喫茶スペースも併設している『メゾンはこしま』。ここには箱崎縞を使った様々な商品が並び、こだわりのお菓子や珈琲でくつろぐこともできる。箱崎縞の優しさや丁寧さに似たテイストを、喫茶のお菓子やドリンクからも感じることができる。
そして実際の箱崎縞を手に取って驚いたのが、洗うたびに柔らかくなり肌に馴染んでいくこと。ともに時間を過ごすことで、徐々に表情が変わっていく様がとてもおもしろい。ぜひとも『メゾンはこしま』に足を運び、箱崎縞を肌で感じてほしい。
デザインも新たに見事に蘇った『箱崎縞』は、海外のお客様からも多くの注目を浴びている。日本だけにとどまらず、世界を舞台に『箱崎縞』は益々の発展を見せることだろう。もちろん『箱崎縞』が生まれた地、箱崎と連携した取り組みも増えていくようだ。
一度は途絶え、幻と言われた『箱崎縞』。古くからの想いを受け継ぎ、軽やかに息を吹き返したこのテキスタイルが、今後どのような広がりを見せるのかとても楽しみだ。
____________________
所在地:福岡県福岡市博多区御供所町12-2-1F
ホームページ:https://www.instagram.com/hakoshima_japon/
この記事の執筆者
ninatte九州の運営事務局です。銭湯跡地、旧梅乃湯を拠点に活動中♨事務局ライター数名で日々記事を更新しています。
福岡県福岡市東区箱崎
『箱崎縞』を機械織で現代に復刻。
「メゾンはこしま」
製造・販売・直売所兼カフェ。