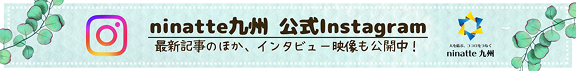徳地の生薬といのちのめぐり 「とくぢ健康茶企業組合」 増田久美子



昼下がり、福岡の自宅で『カワラケツメイ茶』を淹れた。手摘みされている茶葉のひとつひとつの形がきれいで、一口飲むと、じんわりと”いのちのめぐり”を感じる。
街で暮らしていると忘れそうになる、昔からある里山での営み。湯呑みからふわりと薫る湯気とともに、徳地(とくぢ)で暮らす人々の風景が浮かぶ。
佐波川流域で育まれるお茶

残暑が厳しい8月、山口市徳地の山間を流れる佐波川(さばがわ)流域の河原を緑が覆う。
この川の流域には、昔からカワラケツメイ(河原決明)が自生し、その葉や実を焙煎したお茶は江戸時代から親しまれてきた。
「とくぢ健康茶企業組合」では、ノンカフェインでポリフェノールを豊富に含むカワラケツメイを中心に、柿の葉やヨモギなどを生薬(しょうやく)としてお茶にし、現在も地域の特産品として製造・販売・卸業を行っている。つい通り過ぎてしまうほど小さな作業場の前で理事長の増田 久美子さんが出迎えてくれた。

釜で丁寧に煎ったカワラケツメイ茶
作業場に入るとお茶の香ばしい薫りに癒される。収穫されたばかりの茶葉があちこちに干されていた。
「生育状況もあっていっぺんに農家さんが持って来られないから、少しずつ手作業で干しています。運営も結構、大変で・・・世の中、どんどん変わっていきますし」
従業員数名と契約農家さんで協力して生産してきた。なぜこの大変な仕事にたずさわり、続けてこられたのだろうか。
きっかけは徳地づくり達人塾

手作業の工程。カットされた茶葉が袋詰めされていく
「最初は徳地で何かしたいという訳ではなかったんです。そこらへんに生えている草が飲めるなんてことすら知らなかったんですよ」
元々は繊維を欧州へ輸出する仕事をしていた。指導員として海外工場へ行くこともあり、楽しく充実した日々を過ごしていたそう。ずっと、山口で暮らしてきて仕事は順調であるなかで “徳地づくりワークショップ” 参加者の募集を見つけた。
「ここに行けばワクワク、ドキドキする出会いがあるような気がしたんです」
民間からの応募はひとりだけだった。2年後には”徳地づくり達人塾”としての活動となり、続けるうちに塾長になっていた。あるとき健康茶を営んでいる方から、高齢になったことや生薬を加工するための機材の開発などの相談があった。そのことがきっかけとなり有志8名で企業組合を立ち上げることに。会社員を続けながらも組合では出資者として支援だけをしていたが、一年後に赤字になった。
「辞めるか進むかを話し合い、せっかくだから進めようと。ただ、このままの体制では倒産してしまうので、ひとりでもやってみようと思い製造現場に入りました」。
徳地のために続けるということ

収穫前、豆のさやが実る
「生産者もカワラケツメイ茶も資金も、足りない尽くしのスタートでした」佐波川流域に自生していたカワラケツメイだが、護岸工事や農薬の影響で年々減少していた。
「種をかきあつめるのが大変でした。自生の種で育てては増やしながら、少しずつ地元の種を増やしていきました」
そのうち組合員も高齢化し、やむなく理事を降りたいという人も出てきた。運営を続けるために何とか待ってもらえるようお願いをしたそう。
「あまりにも大変だから、本当にやめようと思いました。だけど、農家さんたちも徳地のために頑張ってくれているから途絶えさせてはいけないと思って」。

当時を思い出しながら
大変だった時に、徳地造り達人塾を支援していた山口市の中山間活性化推進室から連絡があった。地域おこし協力隊を受け入れてほしい、そのための支援をしていきたいと。
形にしたいことを資料にすると評価され「これならやっていけるだろう、地域のために思うようになってみなさい」と背中を押してもらい、そのおかげで裁断機や乾燥機を導入できたそう。
「絶対に途絶えさせてはいけない」と気持ちを奮い立たせた。
長年、地域のために活動してきた増田さんの努力と経験が信頼となり支援へとつながったのだろう。
新しい風と共に

袋詰めしていた都野 了瑚(つの りょうこ)さんはお茶が好きだという
環境が整いはじめ、「誰か手伝ってくれないかな」と話していると、若い人が紹介で来てくれるようになった。
「仕事ははっきりいって大変なので、手伝ってくれることには大歓迎です。一次産業だけでやっていくのは厳しいので、生産にたずさわっていただきながら将来は隣接するカフェを開きたいなって話しているんです」。
『生薬の里づくり』をテーマに栽培しながら、商品化やカフェの運営を地域の生業にすることが増田さんの次の目標だ。
「高齢者の方には枝から柿の葉っぱを取る作業をしてもらっています。手作業だからちょうどいいんです。世間話をしながら3時間程お茶づくりをすると給与明細が出て収入になるんですよ。高齢者の方は社会参加の場が少ないので喜ばれてとても元気になられます。
それから、小学生がカワラケツメイを研究材料として見学に来てくれています。子どもたちのためにも守っていかなければと思いますし、徳地を守ろうという思いだけではなく生業にして還っていくようにすることが目指すところです。」
葉っぱがお金になるなんて

刈り取ったばかりのカワラケツメイを束ねる、牛見 真さん
従業員でもあり、生産者でもある牛見さんが畑へ案内してくれた。
「ここは僕の地元で、コロナで仕事が休業になったのをきっかけに手伝い始めました。今でもこれ1本では食べていけないから、夜はバイトをしています。だけどこの仕事が好きだから続けられるんですよ」。
カワラケツメイを作り始めてはや4年目、今年は天気が良すぎて熟れるのが早いという。
「この2列をさっき刈ってきたんです。毎年失敗を重ねながらも、もう少し上手く出来るんじゃないかって工夫するのが面白くて」。

牛見さんの畑には美しい里山風景が広がっていた
「僕は、どうやったら楽に出来るかをずっと考えているんです。しんどかったら続けられないんで。けど現状はなかなか変わらないです。簡単にはいかないかもしれないけれど、楽に出来る方法があれば栽培してくれる人も増えるんじゃないかなって思うんですよ」
それぞれの農家さんと情報交換をしながら、経験を積み重ねていく牛見さん。
「葉っぱがお金になるって、面白いですよね」
増田さんの思いを受け継ぐ人たちが、徳地の新しい風となり吹き抜けていくのを感じた。
ツマグロキチョウが生きる里山

干したカワラケツメイと希少種ツマグロキチョウ(絶滅危惧種)
作業場に戻ると増田さんが「カワラケツメイに蝶がとまっているよ」と教えてくれた。
「こんなところで休むなんて珍しいわね、ツマグロキチョウですよ。カワラケツメイを餌にして生きているんです。自生地が減り途絶えそうになっていたのだけど、去年くらいからすごく増えましたね」
栽培するうえでは葉っぱを食べるから害虫にはなるが、昔からこの里山でずっと一緒に暮らしてきたから保護しているという。
「こぼれ種を少しずつ残してもらっています。蝶の幼虫がカワラケツメイしか食べられないの。ツマグロキチョウが飛んでいるということは無農薬だという証拠なんです」
途絶えそうになっていた里山に、ひとも蝶も戻るとき
そこに暮らすひとたちの生き方もめぐり始める。
「私はもう71歳になるんですよ。どこまでやれるのかなと思っているんですが、若い人たちが本気だから・・・」
生薬の里、徳地でいのちのめぐりを継ぐひとたち。
傍にとまっているツマグロキチョウも徳地の未来を見つめているのだろうか。

理事長 増田 久美子さん
とくぢ健康茶企業組合
所在地:山口県山口市徳地小古祖871
facebook:https://www.facebook.com/ocha1092
ホームページ:https://ocha1092.jimdofree.com/
※お茶のラインナップはコチラから
この記事の執筆者
佐賀県武雄市出身♨️自然と人とのつながりや恵みを伝えることをライフワークにしています。