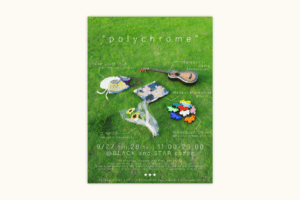「無駄の中にこそ、人生の彩りはある」——画家・杉谷馬場生の哲学と、福岡アートを育む情熱

効率が求められ、あらゆる物事に「意味」が問われる時代。私たちはいつの間にか、心の中の「余白」を失ってはいないだろうか。
福岡を拠点に活動する画家、杉谷馬場生さん(すぎたに・ばばお)。彼の作品は、そんな現代に生きる私たちに、そっと息をする場所を与えてくれる。彼が描き出すのは、卵や亀、魚といった、どこかユーモラスで愛らしいモチーフたち。しかしその根底には、「人生に直接必要ではない“無駄”こそが、世界を豊かにする」という、深く、そして温かい哲学が流れている。
「絵を描く人」——ごく自然に始まった道筋
チラシの裏に夢中で描いたウルトラマンや仮面ライダー。落書きから始まった彼の歩みは、中学・高校、そして短大と、まっすぐに画作の道を進んでいく。
傍らにはいつも絵があった。

転機は、福岡・赤坂にあった画材店でアルバイトをしていた頃。同僚の写真家に誘われて参加したグループ展。そこで彼は、初めて「鑑賞者」の視線と出会う。自らの作品の前に立ち止まり、じっと何かを感じ取ろうとしてくれる方の存在。その喜びが、彼を表現者として生きていく道へさらに導き、『描く営み』へと踏み出させたのだという。
名前に込めたルーツと歩み
実は、活動初期は「VAVAO(ババオ)」という作家名を使っていたのだそう。これは高校時代に友人たちから呼ばれていたあだ名に由来するとのこと。友人との思い出である愛称「VAVAO(ババオ)」と、家族のルーツである母方の姓「杉谷」を組み合わせたのが現在の作家名。それは、彼の創作が、人との繋がりの中で育まれてきたことを象徴しているように思える。

個展やグループ展を重ねるごとに、その名前は少しずつ福岡のアートシーンに浸透していった。やがて福岡を越え、九州各地の展示にも参加するようになり、今では県外のギャラリーやコンペへの出展も増えているのだそう。福岡に根を下ろしながらも、常に視野を広げ、挑戦を続ける杉谷さん。
これまで、自身の決めた描く表現者としての歩みを緩めることもあったのだろうか。
創作の難しさと価格の葛藤

「作品をつくることは、頭の中のイメージを画面に再現する作業です。でも、思い描いた通りに形になるとは限らないんですよ。だから数を描き、試行錯誤するしかないんですよね」。
創作の道は、決して平坦ではない。杉谷さんの活動も一見穏やかに見えて、実は葛藤の連続だったのだそう。
自信を持って臨んだ個展に、思うように人が集まらない日もあったという。作品の価格と、鑑賞者が感じる価値との間で葛藤することも一度や二度ではない。
「自分にとって適正だと思う価格でも、お客様にとっては高いと感じられることがある。でも、同じ値段でも喜んで買ってくださる方もいるんですよ。少し複雑な気持ちになりますよね」。
現在はキャンバス作品を3~4万円台で販売することが多いというが、将来的にはスーパーの特売のように「安く売ることも作品の一つ」として、その取り組みに挑戦する構想も持っているのだそう。
「安く売る行為そのものをアートにする」という発想。 少し斬新すぎるとも思えるが、これは彼らしい逆転のユーモアと探究心の現れなのかもしれない。
展示の集客方法も時代と共に変化しているという。初期は、はがきやDMを一枚一枚手書きで送り、時に数百枚を投函することもあったという。しかし現在はSNSが中心で、InstagramやX(旧Twitter)で情報を発信することが活動の大きな柱になっている。それでも彼は「SNSだけでは完結をせずに、ぜひ実際に作品を見に来てほしい」と強調する。作品の前に立った時の空気感や筆の質感、画布に残る手の跡――それらは小さな画面ではどうしても伝えきれないからだ。
「絵だけはやめるなよ」——父の言葉と、創作の灯火

2006年には初の個展を開催。以来、試行錯誤を重ねながら、一本の道を歩み続けた20年。 その間「本気でやめよう」とは一度も思ったことがないのだそう。そこに、家族という揺るぎない支えがあったから。特に、転職を考えていた時期に父がかけてくれた「絵だけはやめるなよ」という一言。 この言葉は、今も彼の心に灯る消えない光だ。
惰性に流れそうな時にはふと思い出し、「やっぱり描こう」という気持ちを呼び起こしてくれるのだそう。
「無駄」が持つ社会的な価値——効率主義への投げかけ
あえて「意味のないもの」を描きたいと語る杉谷さん。社会的メッセージ性の強いアートが主流となる中で、彼のスタンスはどこか異色に映るかもしれない。
しかし、ここにこそ彼の作品が持つ、現代における深い「有益性」があるのだろう。生産性や効率が重視される社会で、私たちはいつしか「役に立たないもの」「すぐに結果の出ないもの」を切り捨ててしまいがちだ。「人生に直接必要はないけれど、あるだけで華やかになるもの。趣味や嗜好品のように、無駄こそが彩りになるって思うんです」。
趣味や、ただ空を眺める時間、他愛ないおしゃべり。そんな「無駄」の中にこそ、人間性を回復させるヒントが隠されているのかもしれない。

杉谷さんの描く作品は、観る者に「正解」も求めない。ただそこにあるだけで、私たちの心をふっと軽くし、忘れかけていた遊び心や想像力の解放につながる。それは、効率主義の社会に疲れた心に「余白」という名の栄養を与えてくれることだろう。
「無駄こそが彩りになる」という彼の言葉は、人間らしい豊かさを取り戻すための、ひとつの答えなのかもしれない。
「だけど、『無意味を描く』という行為そのものも、突き詰めれば『意味を探す』営みになってしまうんですよね」と、彼は言う。その矛盾を抱えながらも、それを丸ごと表現することが人間らしい創作だと考えているのだそう。
言葉では割り切れない曖昧さを受け入れる姿勢にも、彼なりの哲学を感じる。
また「知識を持ちすぎないことの面白さ」にも触れる。「例えば昆虫を描く際、写真や資料を調べずに、噂程度の情報を頼りに想像で描いた方がユニークな姿になるかもしれませんよね」。
「正確さよりも偶然性や不完全さにこそ創作の種がある」と語る、杉谷さんらしい考え方だ。
福岡に根を張り、未来の土壌を耕す
アート市場の大きな東京や大阪へ拠点を移す作家も多い中、福岡のアート市場はまだ基盤が整っていないのかもしれない。だからこそ、杉谷さんは「福岡を離れるのではなく、ここで育てたいんですよ」と語る。その言葉には、単なる地元愛を超えた、文化の土壌を自らの手で耕そうとする熱意を感じる。
「福岡を盛り上げたい」。福岡から県外、そして海外へ挑戦し、その成果を地元に還元する。彼の存在は、後に続く若いアーティストたちの道標となり、福岡のアートシーン全体を活性化させる起爆剤にもなるだろう。地元に残って土台を築く覚悟は簡単ではなく、杉谷さんの進む道は遠回りに感じるかもしれない。でも、そこに彼の人間としての深みと、未来への使命感が表れている。
終わりなき挑戦——変化を恐れない芸術家が次世代へ伝えたいこと
ワークショップで技術を教える予定はないのだけど、後進に伝えたい思いはあるという。
「作家は常にオリジナルを突き詰める存在。他人に教えるより、自分だけの“無駄”を追い求めてほしい」。
「効率や正解が重視される時代だからこそ、無駄を抱きしめる勇気も必要だと思うんです。もしも若い世代に何かを伝えるとすれば『遠回りを恐れるな』ということでしょうか。遠回りの中にこそ、その人だけの色や形が生まれものだと思うから」。
その言葉には、20年描き続け、自身のスタイルを貫いてきた人間だからこその重みがある。

さらに彼は「お気に入りの作品ほど早く手放したい」とも語る。「作品に執着してしまえば、その成功体験に縛られて、新しい挑戦ができなくなるって思うんです」。常に前を向き、新しい絵を生み出すために、あえて手元に残さないのだそう。
自らを常にゼロの状態に置く。その姿勢には、変化を恐れずに挑戦し続ける作家の矜持がにじむ。
次なる挑戦
杉谷さんの思いはキャンバスを飛び出し、レシートやトイレットペーパーといった「消えゆく素材」に描くという構想にも広がっていく。それも、彼の挑戦心の一端だろう。「作品は必ずしも永遠に残る必要はないって思うんですよ」。アートの固定観念さえも乗り越えようとする彼の探求心は、私たちに「表現の自由さ」も教えてくれる。
さらに、知識に縛られすぎないことも大切にしているという。「カブトムシを描く時に、写真を見ずに、想像だけで描く方が面白い姿になるかもって思うんですよ」と語るように、常識から一歩外れることで生まれる偶然も楽しんでいるのだ。
人柄に触れて

杉谷さんと話していると、誠実で穏やかな人柄が自然と伝わってくる。声を荒げることはなく、ひとつの質問にも丁寧に考えを巡らせ、真摯に答えてくれる姿勢が印象的だ。彼は自分を大きく見せようとすることがなく、むしろ「まだまだ試行錯誤の途中なんですよ」と笑う。その謙虚さが周囲の人々を惹きつけ、応援したくなる理由のひとつになっている。
アートを生業にするには厳しさも多いはず。けれども、彼は「利益よりもまず『見てもらう喜び』を優先し、その気持ちを常に大切にしたい」と語る。その姿勢は、20年変わらずに彼の根幹に流れているのだろう。観客もまたその誠実さに心を動かされるはずだ。
愛おしい無駄が、未来の彩りをつくる
杉谷馬場生の描く「豊かで、愛おしい無駄」は、きっとこれからも多くの人々の心に温かな彩りを添えていくことだろう。
「無駄の中に彩りを」。彼の紡ぐ絵は、日常に不可欠ではないかもしれない。でも、だからこそ、人の心に余白と温もりを与えてくれる。
そして彼の次なる挑戦が、その歩みが、この町のアートにどのような展望をもたらすのだろう。
期待は膨らむばかりだ。